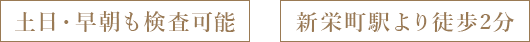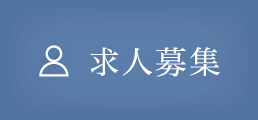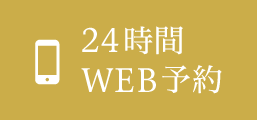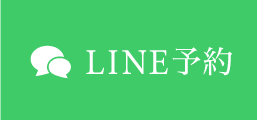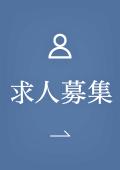潰瘍性大腸炎という病気は、大腸の粘膜上に炎症を引き起こす慢性的な病気です。潰瘍性大腸炎の治療を受けている患者さんにとって、生活の質に影響を与える症状の一つに『おなら』があります。今回は、潰瘍性大腸炎とおならの関係について解説いたします。
潰瘍性大腸炎で
おならが増える原因とは?
潰瘍性大腸炎になると、腹痛や下痢、おならなどの消化器症状が慢性的に生じてしまいます。潰瘍性大腸炎でおならが増える原因は多岐にわたります。
腸内環境の変化
潰瘍性大腸炎が発症すると腸内環境が崩れることがあります。健康な人の腸内は、多種多様な細菌が生息し、バランスよく保たれています。一方で、潰瘍性大腸炎の患者さんの場合ではこの腸内環境のバランスが乱れ、悪玉菌が増えてしまうことがあります。腸内に悪玉菌が増えてしまうと食べた物が完全に消化されなくなり、腸内で発酵されることでガスが過剰に作られることになります。
腸管の炎症
大腸の粘膜で炎症を生じると、腸管の運動が正常に機能しなくなってしまいます。これにより、食べた物が腸内に長く留まってしまい、腸管内でガスが発生しやすくなります。
食事の影響
特定の食品は消化されると腸内でガスが増えてしまいます。潰瘍性大腸炎の患者さんは、大腸粘膜が敏感になっており、特にガスを発生させやすい食品を食べているとその影響が顕著に現れます。ガスを発生しやすい食べ物としては、豆類、キャベツ、ブロッコリー、炭酸飲料、乳製品などがあります。
薬の副作用
 潰瘍性大腸炎の治療では、抗炎症薬、免疫抑制薬、生物学的製剤などが使用されます。これらのお薬は副作用で腸内ガスを生じやすくします。例えば、抗生物質を飲んでいると腸内環境のバランスが乱れてしまい、ガスの発生を促進させることになることがあります。
潰瘍性大腸炎の治療では、抗炎症薬、免疫抑制薬、生物学的製剤などが使用されます。これらのお薬は副作用で腸内ガスを生じやすくします。例えば、抗生物質を飲んでいると腸内環境のバランスが乱れてしまい、ガスの発生を促進させることになることがあります。
腸内ガスの排出障害
潰瘍性大腸炎の患者さんは、大腸粘膜の炎症や大腸が狭窄することで、ガスの排出がスムーズにいかなくなる場合があります。そのため、腸内にガスが溜まりやすくなってしまいます。
潰瘍性大腸炎による
おならの対策について
潰瘍性大腸炎の治療を受けている方で、おならが気になる場合は以下を参考にしてみてください。
食事内容の見直し
腸内でガスを発生させやすい食べ物はなるべく避けるようにしてください。特に以下のような食べ物は控えるようにしてください。また、全粒穀物、フルーツ、ヨーグルト、キムチ、納豆などは腸内環境を整えるために食べるようにしてください。
極力控えて欲しい食べ物
- 大豆
- インゲン豆
- ひよこ豆
- キャベツ
- ブロッコリー
- カリフラワー
- 炭酸飲料
- 乳製品
プロバイオティクスの摂取
 腸内環境のバランスを改善させるためには、プロバイオティクスを含むヨーグルトやサプリメントを摂取することも効果があります。プロバイオティクスを含む食品を食べることで、腸内の善玉菌が増え、ガスの発生を抑える効果が期待できます。
腸内環境のバランスを改善させるためには、プロバイオティクスを含むヨーグルトやサプリメントを摂取することも効果があります。プロバイオティクスを含む食品を食べることで、腸内の善玉菌が増え、ガスの発生を抑える効果が期待できます。
処方内容の見直し
もし飲んでいる薬の副作用が疑われる場合、医師に相談して処方内容を見直してください。薬の種類や投与量を調整する必要があるかもしれません。かかりつけの医師に相談をし、ご自身にあった内容の薬を処方してもらうようにしてください。
適度な運動
 適度な運動をすることで腸管が活発になり、その結果としてガスの排出を促してくれます。決して激しい運動をする必要はありません。ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどでも構いませんので、定期的に運動をするようにしてください。
適度な運動をすることで腸管が活発になり、その結果としてガスの排出を促してくれます。決して激しい運動をする必要はありません。ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどでも構いませんので、定期的に運動をするようにしてください。
ストレス管理
潰瘍性大腸炎はストレスと関係があると言われています。そのため、普段の生活の中で、リラックスできるように、趣味を作ったりしてストレスをため込まないようにしてください。また、睡眠の質も関わってくるかと思いますので、しっかりと睡眠時間を確保することも意識してください。
定期的な受診
潰瘍性大腸炎の治療を受けている方は、定期的に医師の診察を受けるようにしてください。診察を受けて、病状をチェックしていただくことは大切です。症状が悪化し、おならや腹痛、下痢などの症状によって日常生活に支障が及ばないようにしてください。
最後に
 潰瘍性大腸炎が発症してしまうと、下痢や腹痛だけではなく、おならの回数も増えてしまいます。潰瘍性大腸炎の治療でおならの回数が増えてしまった方、何となく最近おならの回数が増えたと思う方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
潰瘍性大腸炎が発症してしまうと、下痢や腹痛だけではなく、おならの回数も増えてしまいます。潰瘍性大腸炎の治療でおならの回数が増えてしまった方、何となく最近おならの回数が増えたと思う方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
当院では消化器内視鏡指導医の資格を持っている院長が、消化器専門外来を行っています。消化器内視鏡指導は日本でも数少ない消化器領域のプロフェッショナルです。当院では院長が消化器専門外来として潰瘍性大腸炎の診察・治療に力を入れています。
潰瘍性大腸炎でおならの回数が増えて困っている方、何となくおならの回数が増えたと思っている方はお気軽にご相談ください。